ライフオーガナイザー
- スカイツリーとともだち
- パッククッキングの会 2025年5月GO MONTHチャリティ企画
- レーシングチームのお片づけ
- 触ったことありますか?AED 普通救命講習Ⅰを受けました
- 「女性のスキルアップ」って、なんですか? 〜家事も育児も、スキルアップが必要なのは誰なのか〜
- 不機嫌をまき散らす迷惑な人になってませんか?
- 気持ちが落ちる時、ありませんか?
- トイレットペーパー、何使ってますか?
- 過去に引き戻される物事はありますか?
- F1 2025年に行ってきた!
-
スカイツリーとともだち

いつもご覧いただきありがとうございます!
先日の上京話の続きです。初体験!小劇場観劇 いつもご覧いただきありがとうございます!先月のことになりますが、ひっさしぶりに上京しまして、観劇してまいりました。こちらの劇場で、初めて、友人の俳優としての雄姿を見る、という目的でした。演目は【CRIMES OF THE HEART】19...時系列としては、正確には観劇の前の話です。始発で最寄り駅を出発して、8時過ぎにひっさしぶりの東京駅に。だいたい品川駅だったんですよね。変わったような変わってないような。相変わらず訳の分からないこと言ってます っていう歌が脳内に流れるくらい人が多いです。自宅付近よりもギュッとしてる印象の東京ですが、ここからスカイツリーのある押上までは小一時間かかりました(笑)。遠くから見てるより広かったんですね。いつも行くところが限られていたので、よくわかってなかったです。10時から展望台営業開始のため、早めに到着しようとしておりまして、始発移動だったんです。この日はあかねちんこと平沢あかねさんを誘っておりました。彼女の夫は転勤族。以前は名古屋にも住んでました。私が初めて出会ったライフオーガナイザー3人のうちの一人で、「めちゃ感じの良い素敵な人やん」「こんな人になりたいなー!」と思ったんです。それ以来、彼女がどこに転居しても、変わらず励ましあって、いろいろ乗り越えてきました。ラジオにも出てもらいました。そんなあかねちんと、カフェで待ち合わせて、ひとしゃべりしてから展望台の列に。 あいにくの曇り空。せっかく展望台に上りましたが、東京タワーですら見えなかったです。
あいにくの曇り空。せっかく展望台に上りましたが、東京タワーですら見えなかったです。 4基あるエレベーター内はそれぞれ東京の四季を表現する装飾があるそうで、これは夏の花火ですね。江戸切子なのかな?とてもきれいでした。
4基あるエレベーター内はそれぞれ東京の四季を表現する装飾があるそうで、これは夏の花火ですね。江戸切子なのかな?とてもきれいでした。コナンの映画公開と時期が重なってたのもあり、ツリーの中はパネルとかがいっぱい。
推し活の若い子たちがたくさん来てました。 ガラスの床部分。他の誘導路は適切でわかりやすく迷うこともなかったのに、ここだけ動線が混乱していて、修学旅行生がうじゃうじゃ滞留。ライフオーガナイザー的には「やり直し!」と言いたくなるマズさでしたが、どうなんでしょうね?
ガラスの床部分。他の誘導路は適切でわかりやすく迷うこともなかったのに、ここだけ動線が混乱していて、修学旅行生がうじゃうじゃ滞留。ライフオーガナイザー的には「やり直し!」と言いたくなるマズさでしたが、どうなんでしょうね?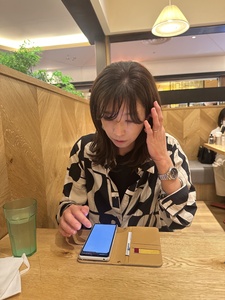 ひと通り見て、早めのランチ。何を食べようか?悩む様子もカワイイあかねちん。体調のこととか、仕事のこと、ちょうどチャリティの準備中だったのでその話とか、いろいろ話して、あっという間に各々次の予定に向かう時間に。ひとりでスカイツリーも行けたけど、付き合ってくれてうれしかったです。そして観劇の後…。よくわからず新宿に行きたいただそれだけで、劇場最寄りの西武沿線から新宿に向かってしまい、バスタ付近までめっちゃ歩くことになってしまったんです(笑)。途中で乗り換えたらよかったんやな。なんやねん東京。遠いがな!スタスタ歩いて、こちらは急遽誘ったかおりんこと塚本香央里さんと合流。かおりんとは、メンタルオーガナイザーの資格認定講座で一緒になり、その後何かがきっかけで距離が縮まったんですよね。私もクラシックを齧ったことがあるので、プロのバイオリニストである彼女の影の苦労がめっちゃわかる。
ひと通り見て、早めのランチ。何を食べようか?悩む様子もカワイイあかねちん。体調のこととか、仕事のこと、ちょうどチャリティの準備中だったのでその話とか、いろいろ話して、あっという間に各々次の予定に向かう時間に。ひとりでスカイツリーも行けたけど、付き合ってくれてうれしかったです。そして観劇の後…。よくわからず新宿に行きたいただそれだけで、劇場最寄りの西武沿線から新宿に向かってしまい、バスタ付近までめっちゃ歩くことになってしまったんです(笑)。途中で乗り換えたらよかったんやな。なんやねん東京。遠いがな!スタスタ歩いて、こちらは急遽誘ったかおりんこと塚本香央里さんと合流。かおりんとは、メンタルオーガナイザーの資格認定講座で一緒になり、その後何かがきっかけで距離が縮まったんですよね。私もクラシックを齧ったことがあるので、プロのバイオリニストである彼女の影の苦労がめっちゃわかる。
会うなり近くのベンチでいろいろと話し込み、寒くなったなぁとごはんに。ここでもいろいろと話しました。ご飯もおいしくて楽しかったー! この日はふたりともに、「ヒラリーは全然気ぃ遣わんで安心しておれるー」とか
この日はふたりともに、「ヒラリーは全然気ぃ遣わんで安心しておれるー」とか「ヒラリー好きよ」など言ってもらって、私の友情が一方通行じゃないことを確認出来て幸せでした。
この後は24時発の夜行バスに乗るまでひたすら人間観察をして過ごし、翌朝6時半過ぎに白子駅に到着!ほとんど寝れませんでしたが7時過ぎの始発路線バスで帰宅して、お昼前にはサーキットでSuper耐久を観てました!なぜ新幹線で当日に帰宅しなかったのか?それは最繁忙期に突入した新幹線に乗るのがイヤだったから。それにしてもこの週は、なぜか大事な用事が集中してしまい、本当に謎ストラテジーでしたが、全部楽しめてよかったです。今日は日記的になりましたが、記録として置いておきます。というわけで、私の発信があなたのヒントになりましたら幸いです。
では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分も配信しています。 -
パッククッキングの会 2025年5月GO MONTHチャリティ企画

いつもご覧いただきありがとうございます!
今日も開催しましたよ!今年も、日本ライフオーガナイザー協会のチャリティイベント【GO MONTH2025】に参加しています!
中部(愛知・岐阜・三重・静岡・長野)の企画は以下の2パターンです。
- 被災地支援プロジェクト
2,200円の募金で、デジタル本「ライフオーガナイザー19人 50通りの片づけ」をお届けします。
私は6ページ寄稿しています。- 暮らしを楽しむプロジェクト
中部各地のライフオーガナイザーが開催する、セミナーやルームツアーなどのチャリティ活動を行います。
私はパッククッキング体験会を開催しました。各地で様々な企画がありますので、最新情報は中部チャプターウェブサイトでご確認ください。
毎月11日開催のパッククッキングの会
今日は、主に中部チャプターの面々と、仲良くしている横浜のLOという、気心知れた仲間と一緒にわいわいと作りました。
 メニューは、
メニューは、- ミネストローネ
- 卵蒸しパン
- ポテトサラダ(じゃがりこ使用)
被災想定で作ります!
- 停電するよ
- 水が出ないし下水にも流せないよ
- 酷い災害だと長期間ゴミ収集も来ないよ
さて、あなたならどうする?っていうことを考えてほしくて、毎月やってます。なんとなく頭ではわかってはいても…
「大災害だから水道は止まってるし電気も付かないよ」、って言ってても、体が勝手に動きます。
ほんとの被災時にいきなり最小限の動きをするなんて、まぁ無理だと思ってください。
ガス・水道を使わないだけで、かなりの制約です。
ついうっかり水を出しちゃうし、冷蔵庫もバタバタ開け閉めしちゃう。
私が「練習、マジで必要だよ」と言ってるのは、ポリ袋調理だけのことじゃなくて、被災期間の過ごし方全般について。
極寒を耐えたり、酷暑をやり過ごしたり、という季節課題もあります。
相当な情報収集と、想像力を駆使したシミュレーションが必要なんですよね。
私もまだいうほどできていません。心配でしょうがないです。
何もない時には話もしづらいでしょうから、このパッククッキングの会をさりげなく話し合う機会に使っていただけたらいいなと思います。
ゴミもこれだけ出ます。さて、お宅はどうします? 考えておくべきことはたくさんあります。
考えておくべきことはたくさんあります。参加者の感想をご紹介
Y.Fさま
以前に1度、レシピを見て作ったことがありました。その時は水道水などを使っていました。今回は意識して作ってみましたが、
・野菜のカット
・鍋の大きさと水量
・段取り
1回では上手くいくはずがないですね。
再度、挑戦したいと思います。
ありがとうございました!T.Uさま
被災時でも美味しいモノ食べたい。いや、被災時ほど美味しいものを食べたいと思います。
出来上がりもとっても良くて多くの方へ知ってもらいたいと思いました。
今回パッククッキングに参加して、大切な事を知る事ができて、常日頃の備えの大切さを感じす。
これからもずっと続けてくださいませ(^^)
企画をしてくださってありがとうございました。
M.Kさま
5回目かな?何度か参加させてもらってますが、また新たな気づきがありました。今回はいつもより水を節約してできることができて嬉しいです。限られたな資源を無駄なくできるよう練習したいです。K.Tさま
なるほど、と思うことがたくさんありました。とても美味しかったです♪地域の人たちにも備蓄の大切さをお伝えしたいです。ご一緒したみなさんと作業することがとても楽しかったです♪
次回はお米を炊いてみたいです。K.Hさま
パッククッキングという調理法だけでなく、水が使えない想定など自分ではなかなかチャレンジしない状況で参加することができていい経験になれました。
これは続けるのに意義がありますね。ありがとうございました。いろいろと、考える機会にしてもらえたようで、よかったです!レシピシート プレゼント!
パッククックは出来上がるまでは味見ができないんです。
なのでレシピが超重要。
ですが、ネットに頼ろうとしても、停電時に検索できるとは限らないし、できるだけ端末の電池消耗を抑えないといけません。
そこで紙のレシピが大切になってきます。
でも、自分でいちいち書くのは面倒でしょ?ということで、アンケートにお答えくださった方には、私が作ったものを差し上げています。
出来上がりを試食して、「うちならもうちょい甘いな」とか「これはちょっと辛かったな」というのを記録しておいて、次回に生かしてもらいたいのです。
好みに合わせた調味料の配分は、忘れないうちに必ず書き留めてほしいです!
作ってみて、食べてみての気づきをしっかりメモに残してもらい、ぜひ改良して「我が家の味」を簡単に再現していただけたらと願います。
毎月11日にやってます
私は超絶心配性。子どもの生活力を高めて、社会で役立つ人として守り育てていくために、私は何をどうしておくべきか?そのことばかりを考えています。災害が起きた時、私は子どもたちと共に、生き延びる術を身につけたと言えるだろうか?まだまだ、全然です。そんな自分自身のためにやっていることなので何度参加しに来ていただいてもOKです。初めて湯煎調理にチャレンジする方を増やしたいと考えております。毎月11日の10時半から無料でやってます。とりあえずいっぺん、やってみていただきたいと思います。実際やり始めてから、わからないことがいっぱい出てくると思いますので、遠慮なくご質問くださったらけっこうです。
まだ次のメニューは決めてませんが、次回はまたごはんを、と思います。次回のお申し込みはこちら→パッククッキング 2025/06/11 10:30-12:00
非常食の備蓄もいいけれど…
冷蔵庫の中の物を使い切る
備蓄食材もそうですが、冷蔵庫の中には調味料も入ってますよね。停電したら使ってしまわないともったいない。だったら日頃から自分たちが安心して食べてる料理が作れる、最低限の調味料だけにしておかないともったいないですよね。使用頻度の少ない調味料は極力買わずに自作するのがいいように思います。冷蔵庫の中は、いつも見通せるように、ポケットの中も詰めすぎないように。
いつも使うものを、使う分だけ入れておくようにすれば、すぐ見つけられて食品ロスもなくなりますし、電気代も抑えられますね。片づけが苦手な方でも、冷蔵庫からなら片づけられる場合があります。
私がオンラインで冷蔵庫の片づけをお手伝いできますので、ご希望の方はご相談ください。とにかく慣れて、備える
パッククッキング、そこそこにできるまで、私も時間がかかりました。なかなかおいしくはできないものでした。でも、私が諦めてしまって、非常事態に途方に暮れることになったら?もっとがんばっておけばよかった、と後悔したくありませんでした。だから、ここまでやってきました。続けてやってきたからこそ、ひとりはなかなかできないということを知っています。
なので、無理にがんばらずに私と一緒にやってみませんか?というお声かけをしています。必ずおいしく作れるようになりますよ。では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分も配信しています。 -
レーシングチームのお片づけ

いつもご覧いただきありがとうございます!
今日、いつも生協で頼んでいる、味の素の生協限定冷凍1.5倍ギョーザを次男に焼いてもらったんです。次男は、焼きギョーザを作るのが長男より格段に上手なんです。焼くだけなのに長男よ おい、というところではありますが…。なんと!18個入っているはずが13個しかありませんでした。必ずいつもひとり6個ずつ食べていたので、絶対に数え間違いではありません。今日は4・4・5⁈ケンカ勃発か⁈となるところでした。通常ならライン検品で重量不足となりはじかれるものと思われますが(そもそも機械でパッキングしているのに5個も少ないってどうなん)、生協の配送センターに着いた後、手作業で個人別に仕分けされますので、同じギョーザをたくさん何度も掴んでたら、仕分けする人も気づきそうなものですけど、こうしてうちに届いて、食卓に並ぶまで見過ごされることもあるんですね。26cmのフライパンに12~3個しか並べられないんですよね。
次男も焼く時一回で全部焼けたらおかしいと気づけよ、というところです。いつもなら2回焼かないと終わらないのに、1回で済んだのはなんでや?と考えてほしい。こういうところにイラっとしますが、とりあえず明日生協に電話します。さて。今日は、レーシングチームの物の管理
について。共有で使うものが多く、大きいものから超細かいもの、堅いものからウェアまで、毎戦メンテナンス工場から持ち運び、設置して使用してまた梱包・輸送するこれを限られた時間で正確に、忘れ物のないように準備して撤収するのは、なかなかに洗練された仕組みが必要です。いちばん凄いのは世界を飛び回って且つレース数が多いF1なのかな?FormulaEもあちこち行くけど、レース数は多くない。あとは、アメリカ国内で(一部カナダなど隣国開催もあるけど)レース数が多くて、航空便より陸路移動なのかな?というNASCARやINDYCARといったシリーズも相当練られたシステムなんじゃないかなと思います。レースももちろん見たいけど、いつかピットの設営から使用中と撤収作業終了、できたらファクトリー到着収容まで、ずっと観察させてもらいたいなと思っています。 こちらはSuperFormulaのパドックで撮った写真です。たしか開幕前のテストの時だったと思います。昨年から絶好調のチーム、DOCOMO TEAM DANDELION RACINGの、搬送用トレーラー(トランスポーター略してトランポと呼ぶ)横に並べてあったのは(おそらく)ジュラルミン製のケースです。精密機器が多いので、こういったところにもお金がかかってしまいますね。
こちらはSuperFormulaのパドックで撮った写真です。たしか開幕前のテストの時だったと思います。昨年から絶好調のチーム、DOCOMO TEAM DANDELION RACINGの、搬送用トレーラー(トランスポーター略してトランポと呼ぶ)横に並べてあったのは(おそらく)ジュラルミン製のケースです。精密機器が多いので、こういったところにもお金がかかってしまいますね。
京都の伝統チームなんですけど、大所帯のビッグチーム、というわけではなく少数精鋭部隊。
「一見さんお断り」ではなさそうですが(笑)、「慣れたらわかる」という感じの大雑把な図に、思わず笑ってしまいました。私に入らせてもらえたら、もうちょっとわかるように表示できるとは思いますけど。
レース時だけのお手伝いスタッフも多数出入りするサーキットでは、誰もが忙しいですし、いちいち「あれどこ?」「これどこにしまうの?」とか聞いていられません。「見たらわかる!」という仕組みがめちゃくちゃ大事になります。けど、こういった仕組みは、一般家庭でも大切な役割があります。- 見つける時・使う時
今、子どもやパートナーからしょっちゅう「歯磨き粉なくなった!ストックどこにあるん?」とか「遠足にレジャーシート要るけどどこ?」とかもののありかを聞かれてうんざりしている方は、扉の内側などに収納一覧の図説を掲示してみるとよいかもしれません。- 使った後・戻す時
出しっぱなし族にも、引き出しの中に姿置き(スポンジ等、物の型取りをしてスポッとはめる仕舞い方)や、仕舞うものを写真や絵にして底に貼り付けて、定位置管理できるようにするなど、「見たらわかる」状態を作ってみるとよいかもしれません。万人に有効ではありませんが、工場・企業などでよく導入されているので、概ねうまくいく方法なのだと思います。もののありかを聞かれなくなるだけで、だいぶまとまった家事時間が作れます。いっとき大変でしょうが、各自探せるようになる仕組みで、かなりのストレス軽減が見込めます。ぜひ、やってみてください。私は今回のブログを書くにあたって、ダンデのサイトを見たら、リクルート情報が載っていたので、ちょっとダメもとで応募してみようかなと思いました!というわけで、私の発信があなたのヒントになりましたら幸いです。
では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。
ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分も配信しています。 -
触ったことありますか?AED 普通救命講習Ⅰを受けました
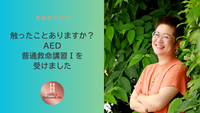
いつもご覧いただきありがとうございます!
突然ですが、あなたはAEDを触ったことがありますか?
最近は身近なショッピングモールを始め、学校や公民館などの公共施設には必ず配置されるようになりました。
「見たことはある」方ばかりかとは思いますが、実際触ってみたことのある方はそんなに多くないようです。という私は、鈴鹿に来てからほぼ毎年、応急処置の講習を受講して、胸骨圧迫による心臓マッサージとAEDの使用訓練を受けております。自分や息子のどちらかに何かあったときのために、子どもたちをお願いするべく、ファミリーサポートセンターに依頼・提供のどちらとしても登録しています。依頼会員は子どもを預ける側、提供会員は預かる側です。私が提供会員にもなっているのは、助けてもらうこともあるかもだけど、助けることができる時はそうしたい、と思っているからです。命を預かるのに、謝礼が微々たるもの。
民間の善意を頼るのはいいですが、ここはもっとしっかりと資金を投入して、質・量ともに向上するべきだと思っています。子どもとの相性があるから、活動登録している人が多ければ多いほど、よりよい保育ができるんですよね。これは里親制度でも同じことで、子どものよりよい居場所を検討できるようにするために、登録者は多い方がいいんです。はい、前置きが長くてすみません。提供会員として、お声がかかったときにはできるだけお応えしようと思っているので、そのためには応急処置として救命講習を受講していなければなりません。なので、毎年開催される一連の講習の中で必ず救命講習だけは受講するようにしています。次は6月にありますので、別に行かなくてもよかったんですけど、わざわざ大阪は門真市まで行って、普通救命講習Ⅰを受けました。場所は、ゆめのたね放送局の大阪スタジオ。前にも書いたか?記憶がないですが、ゆめのたねパーソナリティの中でも防災に興味関心のある人たち(専門家含む)が集まって、防災部をやっております。第一目的としては、収録のためスタジオに訪れるパーソナリティやゲストの方とスタッフ、近隣の住民や、可能であれば通行人の方も、安全に帰宅できるか確認できるまで、一旦避難していただくことを可能にしたいね、ということをきっかけにしていると聞いております。数人が1晩2晩しのげる程度の備蓄を備えることや、日頃から安全に過ごせるようなものの配置、避難経路の確保、避難場所の確認や避難訓練の実施などを活動としてやっていく方向になっております。そんな防災部ですが、パーソナリティの中でもまだ知名度が低く、誰がやってて何をしているか?お伝えしきれていないです。そんな折、共同代表のひとり、私と同級生の佐藤大輔さんが、慢性血栓塞栓性肺高血圧症という病に罹られ、AEDのおかげで助かるという出来事がありました。救急搬送から入院・緊急手術を経てすっかり回復されていますが、通常はなかなか診断も付きにくい症例でありまた、原因不明で完治もしないことから、難病指定されているそうです。診断が付きにくいことから、「なんかしんどい」と思っているうちに亡くなっている方も実は多いのかもしれない病気、ということで、咄嗟の時に救えるかもしれないAEDを設置するためのチャリティ企画が立ち上がりました。それがミリオンハートプロジェクトです。
画家の橘ナオキさんによるハートのポストカードを1枚3,000円で販売し、経費を除く売り上げをすべてAED購入費用に充てるとのこと。カードはすべて違うのものなので、ビビっときたものを選べるのがおもしろいです。ただ、企画としては、AEDを寄贈・設置して終わり、というのではあかんのでは?という意見から、AEDを使える人も増やす活動をしよう!となって、今回の救命講習開催の運びとなりました。交野・門真の消防組合から、普段は救急車を運転しているという救急隊員の方にお越しいただき、まずは座学から。 続いて胸骨圧迫実習と、コロナで止めていた人工呼吸指導の復活(シート使用)
続いて胸骨圧迫実習と、コロナで止めていた人工呼吸指導の復活(シート使用)
普段は30名規模での講習のところ、贅沢にも8名で指導いただけたので、途中おばちゃんたちでアホほど質問しまくりまして、大変有意義でした。
119ダイヤルして、後はAEDさえあれば、指図に従うだけでいいので、何はともあれAEDを探しに行く・行ってもらうことが大事です。私は回数をこなしているため、手順や使用にも戸惑うことはなかったのですが、初めてだと、順番を間違ったり、協力を呼びかけるのを忘れてもくもくと胸骨圧迫を始めそうになったり。練習だから笑えますが、実際に人が倒れていたらこんな緊迫緊張ではないので、練習で失敗しておくことや、触ったことがある、という経験だけでもしておくべきだと思います。その他にも、よくある事故や傷病への対処方法、救急車の使用方法についても教えていただきました。防災ポーチにビニール袋と使い捨て手袋を足さないとな、と思いました。救急車を呼ぶかためらうものの、実は一刻を争う症状・発作について知れて、本当によかったなと思います。
ちょっと幼い顔つきが角田裕毅似の救急隊員さんは、おばちゃんらの勢いに負けることなく、親切丁寧にご指導いただきました。ありがとうございました。
大阪のおばちゃんに全然負けないだけの修羅場を踏んできているんだなと、言葉の端々から感じました。今回は初!消防署による講習だったので「市民救命士認定証」をいただきました。やっと形に残せてうれしいです。AEDのある場所を検索できるアプリもあるので、みなさんぜひ家の近くの設置場所を調べておいてください。出先でも、闇雲に探さなくていいから、安心です。助けたのに訴えられたら…とか言って見過ごすのは、人としてどうかと思います。見なかったことにしても、その人に重い後遺障害が残るとか、死んだら死んだで、遺族から救護義務違反について追及させるかもしれないです。
見ぬふりして後悔したり責められるくらいなら、私は「命あっての文句」、好きに言わせておけばいいと思います。咄嗟に人を助けられる人、私はとても信頼できると思いますので、職場や消防署での受講機会を探して、参加してくださる方が増えたらうれしいです。というわけで、私の発信があなたのヒントになりましたら幸いです。
では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。帰りに、うちのたこ焼き粉としのぶさん家の粉を販売している店長のあやのちゃんに会ってきました。めちゃくちゃよく働き、明るく朗らかな性格でたくさんの人に愛されている、パーソナリティでPAさん。慌ただしく話して、急いで帰宅。
元気もらえました!
寝屋川?香里園?近辺にお住まいの方はお尋ねくださいね。
ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分も配信しています。 -
「女性のスキルアップ」って、なんですか? 〜家事も育児も、スキルアップが必要なのは誰なのか〜
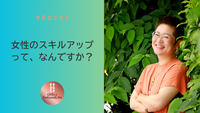
いつもご覧いただきありがとうございます!
本日は、ちょっと一言モノ申すブログとなります。
ここ数日、「女性のスキルアップが必要だ」という発言を、とある政治家がした、という報道がありました。
以前から度々、立場ある男性がこういった発言を繰り返しているのですが、
そういうものを聞くたびに私は、「これ以上何をさせたいの?」と、心の中でつぶやいてしまいます。もちろん、個々の女性として「学び続けたい」、「成長したい」という気持ちは、私自身も大切にしていることです。
キャリアアップしたいだとか、もっと長時間働きたいだとか、もっと効率よく稼ぎたいだとか、願うことは様々だと思います。スキルアップが無意味だとか、不要だと言いたいわけではありません。
ですが、「女性の」と強調されることで、ここに大きな違和感が生まれます。
しかも、「育休中のスキルアップ」について語られるたびに、「はぁ?」となります。
なんでいっつも「女性」やねん?
なぜ、いつも「女性」ががんばる前提になっているのでしょうか。
社会のため、家族のため、職場のため――、気づけば、女性はいつも男性以上に「何役も」担わされているのが現実です。
家では、家事、育児、介護。
外では働きながら、PTAや自治会などの地域活動にも参加しているにも関わらず、そのうえ自己研鑽としてスキルアップまで求められるとは?
元来多くの役割を当然のようにこなしているのに、なぜさらに「女性の努力」が求められるのでしょうか。
そもそも育休とは、放っておいたらすぐに死んでしまう新生児・乳幼児の命を、24時間休みなく見守らなければならないがために必要な休暇であって、「家にいるから合間に勉強できるよね?」と言ってしまう男性の【わかってなさ】にほとほとうんざりしているんです。だから、私は
「仕事 し か していない男性こそ、家事や育児のスキルアップをするべきでは?」と思います。
女性ばかりに努力を求める構造に疑問を持ってほしい
「女性の社会進出が進んでいる」とよく言われますが、実態はどうでしょうか。
女性が社会で活躍するには、「家庭のことはきちんとやってから」という前提がいまだに根強く残っています。
一方、男性はというと、家事ができなくても、育児に関わらなくても、「仕事ができればOK」と評価されることが多いのではないでしょうか。
しかも、職場の評価では「仕事しかしない男性」と比べて「家事も子育てもしている女性」だと、「仕事しかしない男性」の方が評価される制度が一般的です。
「は?」ですよね。仕事にフルコミットできる方が有利に決まっています。こういった矛盾が、多くの女性を苦しめているのです。
妊娠・出産のたび、社会構造で女性のキャリアが分断される状態を放置しておきながら、もっとがんばれとは何ごとか?女性だけがスキルアップすべき、という前提そのものが、すでにおかしいと思うのです。
家事や育児は、「誰かの役割」ではなく、すべての人のライフスキル
私は、ライフオーガナイザーとして、「思考の整理から始める片づけ」を提唱しています。
けれど今こそ、日本社会全体が「思考の整理」を必要としているように感じています。
家事をする=女性だから当たり前、
育児に関わる男性=やらなくていいことをやって偉い、
といった、時代遅れな価値観は、もう手放すべきです。
家庭を維持するために必要な家事や育児は、性別にかかわらず、すべての人にとって必要な「ライフスキル」なのです。
それを「女性がやるべきこと」として押しつける構造が、今なお根強く残っている現実。
自分のこともできないオジサン・オジイサンだけでなく、そんなオジサンたちを増長させてきた《女性であるオバサン・オバアサン》までもが時代錯誤な「こうあるべき」を押し付けて来るんだから、今の子育て世代はたまったものではありません。この構造を見直さずに、「女性のスキルアップ」ばかり叫ばれても、的外れ感しかありません。
そもそもは、家事も育児もできない「男こそ、一人前の大人になれるようにスキルアップするべきなんだぜ?」と思います。社会を変えるには、まず「声を上げること」から
こうしてブログに書くことも、私なりの「声を上げる」手段のひとつです。
同じようにモヤモヤしているけど、うまく言葉にできないという方の、代弁ができたらと思っています。
今こそ、「なぜ女性ばかりが何重もの多大なる責任を負わされるのか?」という問いを、遠慮せずに投げかける時ではないでしょうか。
「男性も変わるべき」「社会の仕組みそのものを見直すべき」という声が、もっと大きく、もっと当たり前に語られるようになってほしいと思います。
女性のスキルアップが「社会構造を変えずに、女性だけに努力を押しつけるための方便」になっているなら、それは違うと言いたいのです。
本当に必要なのは、「女性のスキルアップ」ではなく、「男性の意識改革」、
そして社会全体の構造のアップデートではないでしょうか。すべての人が、当たり前に暮らしを担い、生活と向き合い、自分の人生を整える。
そんな社会に、一歩ずつ近づけていきたいと、私は心から願っています。めっちゃ熱く語りましたが、私の発信があなたのヒントになりましたら幸いです。
「そうだそうだ!」とご賛同いただけましたら、ぜひシェアしていただけますとうれしいです。そして選挙の際はぜひ投票に行きましょう。
議会で寝てばかりの高齢男性が好き勝手する現状を変えましょう!では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。
ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分も配信しています。 -
不機嫌をまき散らす迷惑な人になってませんか?
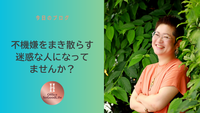
いつもご覧いただきありがとうございます!
今日は、まじめに考えてみた系でございます。
堅い内容と表現となっております。[#機能置換タグ_TOCCLOSE:目次(クリックすると開きます)#]夫が自分の機嫌を取れない家庭の悪循環と、その解決策
家庭内で夫が不機嫌をまき散らすことに悩んでいる女性は少なくありません。
会社では一定の態度を保てるのに、家では不機嫌を隠そうとしない。
これは一体何どういうことなんでしょうか?夫の不機嫌が家庭に及ぼす影響は大きく、妻や子どもにとって深刻なストレスの原因となります。
特に、「自分の機嫌を自分で取る」という習慣がない夫の場合、その影響は家庭だけでなく、夫自身の幸福度や社会的な関係にも悪影響を及ぼします。
ここでは、夫が不機嫌をまき散らすことによる問題点、なぜ妻をはじめとする家族に対してそのような態度を取るのか、そしてその解決策について考えてみます。
夫の不機嫌が家庭に及ぼす悪影響
家庭の雰囲気が悪化する
夫の機嫌が悪いと、家全体がピリピリした雰囲気になります。
家族全員が夫の顔色をうかがうようになり、自由に意見を言ったり、リラックスした時間を過ごしたりすることが難しくなります。
妻の精神的負担が増える
夫が自分の機嫌を取れず、不機嫌をぶつけると、妻はその対応に追われます。
機嫌を取ろうと気を遣ったり、余計な争いを避けるために我慢したりすることで、妻自身のストレスが増大します。
子どもに悪影響を与える
家庭の空気が重くなることで、子どもも萎縮しがちになります。
安心して自己表現ができない環境では、子どもの自己肯定感が低くなり、親子関係や将来の人間関係にも悪影響を及ぼします。
また、子ども自身が「怒りで感情を表現する」ことを学んでしまう可能性もあります。
夫婦関係の悪化につながる
不機嫌をまき散らされる側は、次第に耐えきれなくなります。
夫が何も考えずにイライラをぶつけているうちに、妻の気持ちが冷め、夫婦間の溝が深まってしまうことも少なくありません。
なぜ夫は家庭でだけ不機嫌をまき散らすのか?
多くの夫は、会社では感情をコントロールできているのに、家ではそれができません。
これは、家庭では「甘え」が許されると思っているからです。
社会人として職場での振る舞いを意識している間は、相手に敬意を払うことができるのに、家に帰るとその意識がなくなり、気を抜いてしまうのです。
この背景には、妻に対する無意識の「軽視」や「甘え」があるのかもしれません。
「家族だから、何をしても許される」「気を遣う必要がない」と思っていると、知らず知らずのうちに妻を都合の良い存在として扱ってしまうのです。
しかし、これは大きな間違いです。
家族こそ、最も大切にするべき人間関係であり、最も配慮を必要とする関係です。
夫が自分の機嫌を取れるようになるとどうなるか?
家庭が穏やかになる
夫が自分の感情をコントロールできるようになると、家庭の空気が一気に変わります。
妻も子どもも安心して過ごせる空間が生まれ、夫自身もリラックスできる場所を持てるようになります。
妻のストレスが減る
夫の不機嫌に振り回されることがなくなれば、妻は精神的に安定し、より健やかな関係を築くことができます。
夫婦関係の改善にもつながります。
子どもの情緒が安定する
家の中で安心して過ごせる環境ができれば、子どもは健全に成長できます。
親の顔色をうかがうことなく、自分の感情を素直に表現し、自己肯定感を高めることができます。
夫自身の幸福度も上がる
「自分の感情を他人にぶつけるのではなく、自分でコントロールできる」ということを学べば、夫自身のストレスも減ります。
結果的に、仕事や友人関係、社会生活にも良い影響が生まれます。
夫が自分の機嫌を取るためにできること
自分の感情を自覚する
「なぜ自分はイライラしているのか?」を言語化することが大切です。
日記をつけたり、気持ちをノートに書いたりするだけでも、自分の感情に気づきやすくなります。
ストレス解消の習慣を作る
運動をしたり、趣味の時間を持ったりすることで、ストレスを上手に発散することができます。
「自分の機嫌は自分で取る」と決める
他人に自分の感情の責任を押し付けるのではなく、自分の気持ちは自分で管理するという意識を持つことが重要です。
パートナーを尊重する
家族こそ大切にし、敬意を払うべき存在です。
妻を「甘えられる相手」ではなく、「共に人生を歩むパートナー」として尊重することで、自然と態度も変わります。
家庭は、誰もが安心して過ごせる場所であるべきです。
夫婦がともに成長し、よりよい関係を築いていくためにも、「自分の機嫌は自分で取る」ことを心がけていきたいものですね。
男だから、夫だから上司だから父だから…そんな区分や役割にとらわれず、自分が心地よいと思うペースで生きていけるように、無理せず、ラクに、折れない心を育てていきましょう。では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。
ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分もSpotifyにて配信しています。 -
気持ちが落ちる時、ありませんか?
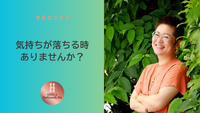
いつもご覧いただきありがとうございます!
先週、妹の代わりに退院する母を迎えに、兵庫県の西宮市まで行って、メンタルに大ダメージを被った話をInstagramストーリーで触れました。2つ前のブログでもちょっと書きました。私が離婚を前提の別居をするとき、母と妹たちが「近くにおいで。何かとサポートできると思うから。」と言うので、愛知県から地元に住むことにしたんです。しかし、引っ越しの片づけをしつつ生活の基盤を整えようかと作業している時に、「突然話がある」と呼び出され、「宗教上の理由で今後一切関わらない。孫は悪くないから預かってもいい。」と通告してきました。いちばんしんどくて、ただ話を聞いてくれるだけでも、という時に切り捨ててきた母と妹。しかし、そうしなければならないことは、あの宗教の掟、というか行動基準として、以前から私を含め誰もが知っていることだと思っていたし、わかったうえで私を受け入れようとしているものだとばかり思っていたので、彼女らから「先日初めて長老から警告されて知りました」的発言があって、「なめとんのか?アホなんか?私の人生なんやと思ってんねん!そんなことなら地元には戻らず、愛知県内で頼れる人と関わりながら子育てする方が100倍よかったわ!」と怒りに震えました。そもそも宗教も、母に認めてもらいたくて、喜ばせたくてやっていたもの。思ってもないことを戸別訪問して言わなければならない苦痛に耐えかねて「辞める」と宣言した経緯があります。その時に、母が、「正式脱退は縁を切らないといけないからやめてほしい」と謎の要求をしてきました。辞める時のルールだから手続きしないといけないのでは?と思ったけど、その時は「そんなに言うなら」と有耶無耶のままでフェードアウトさせました。結局まぁ、曖昧は良くなかったんでしょうね。
正式にはやめていないのに、やめた人のように生活していたので、数々の規律に違反していました。
絶縁通告の理由はそういうものです。それまでは漠然と、「この人と一緒にいてもいつも孤独を感じるのはなんでだろう?」とずっと思ってきましたが、母は「変わりたいとは言うけど実は変わりたくない悲劇のヒロインタイプ」の自己中人間か?ということにだいぶ経ってから気づいたんです。
いつまでもどこまでも「あの人がこうだからああだから」という愚痴を幼い頃から聞かされて、父のことも祖母のこともグチグチ言い続けて、その上「私を見て!こんなにがんばってる私をほめて!」と暗にいう母。私が小学校の頃から学校でのことを何も話さなかったのを、「しっかりしてるから・特に問題がないから」と誤認していた母。あなたが自分で精一杯だったから言っても無駄だと思ってたんですよ。そんな関係なので、心理的・物理的に距離を置くために、鈴鹿に来たというわけです。私はそんな母の面倒を見るつもりは全くなくて、妹が困ってると言うから、できることはやってあげようと長距離の運転手をかって出たわけなんですが。妹には妹の言い分があるんでしょうけど、非常にがっかりする対応があり(まだ状況説明や謝罪はない)、それを見ていた父の反応にも非常にがっかりしました。「何だろうか?この噛み合わなさは?」まともじゃない家に育った自覚はありますが、出た今、さらにあの人たちの異常さが怖いなと思います。内省がないと、成長しないし、周りとのズレや、どう見られているか?も気にしないし(気にしてたらあんな宗教はできないんですけど)。
ちょっと見た目にはまともそうに見えるのがほんまに怖いです。モラ夫とかDV夫とかみたいなもんです。
宗教という自分だけの正義を振りかざして、平気で人を傷つけているのに全く無自覚で、なんなら被害者面します。だからこそ、私はライフオーガナイズの「私はこうだけど、あなたはそうなんだね。どっちもいいよね!」みたいな考え方に救われたというか、受け止めてもらえたような、「ここにいてもいいんだ」、と感じられたんでした。ちょうど1週間たって、落ちた気持ちも多少フラット寄りに戻りましたが、PMSなのか気持ちが揺れる時期で、ちょっとのことで涙かこぼれます。そんなタイミングで見ている『しあわせは食べて寝て待て』というNHKのドラマがまさに20年くらい前の私。働いてもお金がなくて、働いたら消耗して。私は薬膳じゃなくてマクロビオティックをやろうとして挫折しました。
なんせ全部高い。
主人公はまるで私。桜井ユキは私です。当時の私が思っていたことが、たくさんセリフとして出てきます。思い出してしまって勝手に涙が出ます。そういう時期だからしょうがないですが、とてもよくわかっている人が脚本を書かれているんですね。
それか原作がよいのか。つらつらと書いてきましたが、- ドラマよいですよ
- 気持ちが揺れるのは当たり前のこと
- 悲しい出来事もいつか感情とは切り離して手放せる
が伝わったら幸いです。というわけで、私の発信があなたのヒントになりましたら幸いです。
では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。
ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分も配信しています。 -
トイレットペーパー、何使ってますか?
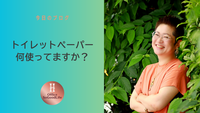
いつもご覧いただきありがとうございます!
先週の鈴鹿日本GPから早くも今日からはバーレーンGPが始まっています。昨日から学校では給食も始まって、日常っていう感じが戻ってきました。
今朝は早くも行きたくない、という次男を送っていきましたけれど…。さて今日は、ちょっと気になるけど、どうでもいいような、しょうもない比較にお付き合いください。みなさんも毎日必ず使う、トイレットペーパーについて。ダブルを使っているリッチなあなたがうらやましい。もし何を言ってるのか?意味が分からない男性がいたら、わかるようになってくださいね。災害時に買えないことも考えて、交換タイミングが長い、シングルの5倍巻きを使ってきたわたくし。
ですが、しばらく前に、拭き取る時のごわつきが気になりだしました。時々、痛いなと感じることもあったので、これはあかん、と思いました。そこで、思い切って贅沢をして(笑)、2倍巻きを使ってみることにしました。
シングルの5倍巻きと2倍巻きで、厚みの違いや使用感の差はあるのか?
ちょっと検証してみようと思いました。 うちで使っている5倍巻きと2倍巻きです。この5倍巻きはマックスバリュでも売ってますね。2倍巻きは生協のものです。どちらも芯なしです。一般的な芯ありのペーパーは50mだとか。2倍だと100m、5倍だと250mです。ソフトさが違う?
うちで使っている5倍巻きと2倍巻きです。この5倍巻きはマックスバリュでも売ってますね。2倍巻きは生協のものです。どちらも芯なしです。一般的な芯ありのペーパーは50mだとか。2倍だと100m、5倍だと250mです。ソフトさが違う?
書いてあるかと思って、裏面を見てみたんですが、幅は書いてあるけど、厚みについては表示義務がないのか、書いてありませんでした。 幅107mmで250mの5倍巻き
幅107mmで250mの5倍巻き 生協のは、普通巻きが60mということで、約2倍の130m、幅は105mmです。ただしこちらには、品質規格表示として、1㎡あたりの重さや、破れに対する評価、ほぐれやすさ、という表示があって、こんな基準で製品評価がされるのか、と知った次第です。興味深い。5倍巻きの方にも表示があれば、厚みやごわごわ感の比較数値が明確だったのかな?と思います。使用感としては、どちらも素人がパッと見てわかるほどの厚みの差はないですし、拭いてみても「わぁ!柔らかい!」ってこともありませんので、私の主観になりますが、2倍巻きの方がちょっとだけソフトなのでは?という気がする程度です。それから、使用期間というか、うちの交換頻度ですが、男2女1の家族構成で、5倍巻きの時は1ロール3週間程度、2倍巻きになってからは約1週間となりました。
生協のは、普通巻きが60mということで、約2倍の130m、幅は105mmです。ただしこちらには、品質規格表示として、1㎡あたりの重さや、破れに対する評価、ほぐれやすさ、という表示があって、こんな基準で製品評価がされるのか、と知った次第です。興味深い。5倍巻きの方にも表示があれば、厚みやごわごわ感の比較数値が明確だったのかな?と思います。使用感としては、どちらも素人がパッと見てわかるほどの厚みの差はないですし、拭いてみても「わぁ!柔らかい!」ってこともありませんので、私の主観になりますが、2倍巻きの方がちょっとだけソフトなのでは?という気がする程度です。それから、使用期間というか、うちの交換頻度ですが、男2女1の家族構成で、5倍巻きの時は1ロール3週間程度、2倍巻きになってからは約1週間となりました。
ちなみに私は月経困難症で治療中。
生理の出血を止めているので、一般女性よりペーパーの使用量は少なめだと思います。ざっと計算すると、1パッケージ6ロールで約1か月半です。うちの場合、1年分は8パッケージあったら足りるということになります。
ストック用のスペースもそんなに必要ないということがわかります。毎月安売りのタイミングに必死で買わなくてもいいんです。めちゃ気楽になりませんか?このように、具体的な数字を出してみることで、漠然とした切迫感から解放されます。コロナ時、噂に惑わされてアホみたいにトイレットペーパーを買い占めた人たちに言いたい。
自分ちの、1か月のトイレットペーパー使用量を把握しなはれ。
とりあえず3か月~半年分あったら、なんぼなんでもそれ以上在庫する必要ないですやろ。同様に、昨秋以降、毎日スーパーに並んで米を買い占めた年寄りたちも。自分の日頃の消費ペースを考えなはれ。1か月で何キロ食べられますのん?5キロもよう食べへんのと違います?米ほど在庫管理に神経を遣う食品はないんやわ。うっかりしてたら、あっという間に虫がわきますやろ。で捨てますやろ?その米を、育ち盛りの子どもたちに食べさせるべきやったんですわ。テレビの言うことを真に受けて、自分の頭で考えなかった、自己中心的で浅はかな愚か者ですよ。このように、自分の暮らしが把握できていなかったら、自分の家が要らないものだらけになるだけでなく、必要としている人からも奪うことになります。無計画に買い占めする人は社会の敵ですよ。困ってる人の足元を見て生活必需品を高額転売する人なんて、ほんまゴミですわ。快適に、効率よく暮らすためには、「自分の必要」を知ることがとても大切です。どうでもいいトイレットペーパー比較から、全然違う自己理解の話に着地しそうですが、自分を知ることは何にしても基本になります。なんとなくもの買っている人は、一度記録を取るところからやってみてほしいです。だんだん楽しくなってくるので!
トイレットペーパーの交換サイクルから、歯ブラシの取り換え、ラップやホイル1本をどのくらいで消費しているか?平均的なタイミングがわかると、明確な行動のサイクルとして買い足しや交換の計画ができます。
暮らしに見通しが立てられると、生活がどんどんシンプルになっていきます。なので、ぜひ、だまされたと思って「記録をつける」ことやってみてほしいです。というわけで、私の発信があなたのヒントになりましたら幸いです。
では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。
ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分も配信しています。 -
過去に引き戻される物事はありますか?
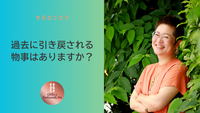
いつもご覧いただきありがとうございます!
私が奈良県天理市の出身であることは、プロフィールにも書いておりまして、高卒で公務員になったものの、20歳で退職、バイト時代を経て20代半ばで転職して、大阪市内に働きに行っておりました。某公共放送の深夜枠に、大阪から奈良の近鉄奈良線の運転席車載映像を流すという番組があったから、懐かしくて録画してみました。
当時、船場で働いてたので、行きは近鉄を日本橋で降りて地下鉄(今は大阪メトロっていうん?)に乗り換えて堺筋本町で下車。今は亡き(笑)マイカルの本社で働いてました。生きる意味がわからん、何のために生きんとあかんのや?って思ってるのに、生きるために稼がんとあかん、だから働かんとあかん、けど働くのめっちゃしんどい消えたいっていう、わけわからんループで、マジでただただ早く消えたい、とずっと思いながら毎日通ってました。いつ消えてもいいくらいどうでもいい自分、大事にされる価値もない、と思ってたので、声をかけてくる人が既婚者ばかりでも、どうせ二番目三番目くらいでしか相手にされない自分だからしょうがない、と思って付き合ってました。
セルフネグレクトちっくですね…。激病み暗黒期。そんな時に職場の先輩が「ゴスペルの体験レッスンに行こう!」と誘ってくれて、それからなんばのYAMAHAに通い始めました。月2のレッスンが楽しくて、全員ガイジンネームを名乗るルールのクラスで謎に付けられた名前がヒラリーでした。
ビバヒルじゃなくてクリントンのほうが由来です。
なんでそんなハイソやねん、って突っ込んでください。並の高卒やし、実は芸名なんです。でも今はビジネスネームとして使っているくらい気に入ってます。めっちゃやっすい給料だったので、元々地下鉄の通勤手当をケチるために回数券を利用していて、行きは堺筋本町まで乗るけど、帰りは徒歩にしてました。本町から心斎橋筋を歩いて難波まで。
全然大した距離じゃないし、商店街とか、御堂筋とか、気分によってルートを選べたし、途中百貨店をのぞいたり、超シンデレラでも買えるサイズを売ってる靴屋さんを探したり(1軒だけ、心斎橋筋に十字屋さんっていうところを見つけました。まだあるかな?)、仕事がしんどくてもなんとか気を紛らわせながら必死で生きてきました。さてさて、近鉄線の話です。近鉄奈良線。
いつも通勤で使ってた路線です。
通勤のためなので、快速急行しか乗らなくて、車載映像の区間準急はイマイチ停車駅がわからず。
けど、見ていたら思い出すもんですね。
今となってはめちゃめちゃ懐かしい。
上に書いたような、いろんな当時のあれこれがうわっ!とよみがえりました。帰宅中の鶴橋駅は拷問並みの焼肉臭で、降りて食べたい!けどお金がない!
途中下車したいのを毎日耐えてました。
そういえばマック(当時はマクド呼び(笑))にもあまり寄れなかったなぁ。ほんとにお金がなかったから、ゴスペルのレッスン料を払うのが精いっぱいで、やりたいことがやれないし、たくさん稼ぐ方法も思いつかなかったし(私なんかを買う人もおらんやろ、とか思ってたし…)めちゃめちゃヤバみあふれる自己卑下マンでした。そしてそこからMLMに闇落ちして自己破産するんですよ…(笑)。これまでの人生で、いい思い出はほんとに少ない(ゴスペルくらい)第二暗黒期を過ごした大阪を経て、兵庫県三田市に転勤したところでF1と出会い、今、どうにか生きております。必死で立て直して、変わる努力をしてきて、何とか安定させて、子どもとも日々いろいろある中でどうにかやっております。あの頃よりはとてもいい毎日です。私は実家に恵まれず、両親妹とも疎遠だし、宗教が絡んで諸々非常に困難を極めております。今日も両親と関わる時間があったんですが、予定していたより酷いダメージを負ってしまいました。でもね。次男に「もう縁切ってもいいと思うよ」って言われて、「そっか。」と思えました。私を大事にしない人と、家族だからって付き合う必要ないよね。私なりに彼らを大切にしてきたつもりですが、私の心のマンションからは、両親と妹をそっと退去させることにします。近鉄線の映像から、よくわからん着地になりそうですが(汗)、心を片づけると過去の出来事と感情を別物として扱うことができるようになりますし、辛かった出来事を何度も反芻してしまって、そのたびに傷ついてしまう、といった事態を徐々に減らして、最後は穏やかな気持ちで「そんなこともあったねぇ…。」といつか笑える日が来るんです。今あなたの脳内に中島みゆきが流れましたか?今日は突如私のダークマターを浴びてビックリされたと思いますが、たぶん明日は大丈夫。私も元気に仕事できると思います。パッククッキングの会がありますし!麻婆豆腐を作ります。よかったら、そんな心の片づけを体感してみてください。メンタルオーがナイズ、めっちゃいいですよ!というわけで、私の発信があなたのヒントになりましたら幸いです。
では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。
ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分も配信しています。 -
F1 2025年に行ってきた!
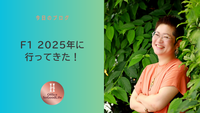
いつもご覧いただきありがとうございます!
先週は、ふわふわと浮かれた一週間でした。なんなら今日もまだ、チームやドライバーの振り返りが流れてきて、ニヤニヤしておりますが。記録として今年の鈴鹿を残しておこうと思います。F1グランプリ2025
今年、私は観戦券を買いませんでした。というのは、土日の観戦は家で、と考えていたからです。普段のレースとは比べ物にならない観客数になり、何をするにもまぁまぁなストレスがかかることと、やっぱりチケットもめっちゃ値上がりしました。
1・2コーナーからS字と逆バンクまで見渡せる、B席上段とか

シケインのQ2席から見るレースはサイコーなんですよね。
でもとてもじゃないけどF1はお高くて買えないです。ここ数年、木曜日と金曜日は、鈴鹿市と周辺の5市町村住民対象の、無料招待事業をやってくれているので、今年はそれでいいかな、と思いました。 メインゲートを入ったすぐのところに、ドライバーたちのパネルを設置してくれていました。推しのフェルナンドアロンソと。鈴鹿サーキットの装飾さんたち、ほんまにすごいんですよ。
メインゲートを入ったすぐのところに、ドライバーたちのパネルを設置してくれていました。推しのフェルナンドアロンソと。鈴鹿サーキットの装飾さんたち、ほんまにすごいんですよ。
 今年はいろいろあって、鈴鹿の1週間前にドライバーの入れ替えが決まりました。角田裕毅とリアムローソンです。チームが違うので当然レーシングスーツも違うから、入れ替わった二人の装飾は仮に前のままでも仕方ないよね、とファンの誰もが思ってたんですが、名古屋駅もサーキット園内も、全部作り直して貼りかえられました。しかもレースに間に合った!幟旗とか、すごい数なのに…とんでもない意地を見せつけたと思います。
今年はいろいろあって、鈴鹿の1週間前にドライバーの入れ替えが決まりました。角田裕毅とリアムローソンです。チームが違うので当然レーシングスーツも違うから、入れ替わった二人の装飾は仮に前のままでも仕方ないよね、とファンの誰もが思ってたんですが、名古屋駅もサーキット園内も、全部作り直して貼りかえられました。しかもレースに間に合った!幟旗とか、すごい数なのに…とんでもない意地を見せつけたと思います。木曜日
木曜日は、セイフティーカーとメディカルカー以外、レーシングカーは一切走らないんですが、午前中は各チームの準備の様子をピットレーンから見られるピットウォークがあります。昼は地元対応で、ドライバーとの交流事業がありました。鈴鹿市の小学4年から6年までの子どもたちがパドックに行って、ちょっと楽しく過ごす、っていう感じです。去年に引き続き今年も次男が協力してくれて、応募したら当選したんです。次男はレースに興味がないのに(笑)ありがとう。
去年はハース、今年はザウバーになってしまい、またニコ ヒュルケンベルグとご対面となりました(笑)。 一瞬だけ貸してもらえるゲストパス(F1パドックパスは100万円越え)
一瞬だけ貸してもらえるゲストパス(F1パドックパスは100万円越え) パスをピッとしないと通れないゲート今回の交流はだるまアクティビティとだけ書いてあって、???となってましたが、ドライバーと一緒にだるまにステッカーを貼っていく作業をしたらしく、各自仕上げたのを持って帰ってきました。写真はF1公式か各チームが撮ったものしかないので、後日もらえるように交渉してくださいました。まだ手元にはないです…。夕方からはドライバーとエンジニアなどチームが、歩きや自転車でコースチェックをする、トラックウォークに出てきます。ファンはコースサイドから声をかけたり旗を振ったりしてアピールします。
パスをピッとしないと通れないゲート今回の交流はだるまアクティビティとだけ書いてあって、???となってましたが、ドライバーと一緒にだるまにステッカーを貼っていく作業をしたらしく、各自仕上げたのを持って帰ってきました。写真はF1公式か各チームが撮ったものしかないので、後日もらえるように交渉してくださいました。まだ手元にはないです…。夕方からはドライバーとエンジニアなどチームが、歩きや自転車でコースチェックをする、トラックウォークに出てきます。ファンはコースサイドから声をかけたり旗を振ったりしてアピールします。金曜日
ここからマシンの走行が始まります。フリー走行の時間は週末に3回あるうちの、2回が金曜にあります。金曜日は、グランドスタンド以外は自由席なので、好きなところから観られます。うちから自転車で17分、10時20分に1コーナーゲートに駆けつけてまずB席に向かい、スタンド下の焼肉ランチの行列(長蛇でも15分くらいで買える)に並びます。キャベツと豚バラを炒めただけの丼ですが、謎に激ウマなんです。たれも売ってるけど家では再現できません…。神戸(かんべ)にお店があるそうで、行ってみようと思いつつ、サーキットだけのお付き合いとなっております。買ってから、忙しなく働いている奥さんにご挨拶して、席の確保に。 あたたかいというか熱い日差しのもと、美味しくいただいて、FreePractice1は2コーナーから。上の方に座ってたお友達に見つけてもらって、一緒に観ました。つのぴーのレッドブル初走行は大歓声、大拍手!なんですけど、つい、こないだまで乗ってたレーシングブルズのマシンが来ると「あ!来た!いや、これちゃうわ」ってずっとなってました(笑)。歳のせいか、アップデートに時間がかかりすぎる…一応、レッドブルも日本スペシャルカラーリングで白っぽくしてきたから、ややこしくなっただけ、ということを付け加えておきます。クラッシュもなく、平川亮君のアルピーヌ初走行も感動のうちに見終えて、GPスクエアに急いで移動。クラフト勢のみなさんの作品を拝見しに行きました。
あたたかいというか熱い日差しのもと、美味しくいただいて、FreePractice1は2コーナーから。上の方に座ってたお友達に見つけてもらって、一緒に観ました。つのぴーのレッドブル初走行は大歓声、大拍手!なんですけど、つい、こないだまで乗ってたレーシングブルズのマシンが来ると「あ!来た!いや、これちゃうわ」ってずっとなってました(笑)。歳のせいか、アップデートに時間がかかりすぎる…一応、レッドブルも日本スペシャルカラーリングで白っぽくしてきたから、ややこしくなっただけ、ということを付け加えておきます。クラッシュもなく、平川亮君のアルピーヌ初走行も感動のうちに見終えて、GPスクエアに急いで移動。クラフト勢のみなさんの作品を拝見しに行きました。 ここ数年、毎年のようにご挨拶している親子さん。たまに別のイベントやレースでも会うことがあって、仲間感が育つのも楽しみなんです。ちょうどお会いしてる時に、読売新聞の取材が来て、お父さんが対応されてました。今年は海外メディアからの撮影やインタビューもすごかったし、何より中学生の彼のガスリー愛が届いて、毎年ピット前に入れてもらってたり、チームガスリーの一員として迎え入れられて、よそのお子さんやのにめっちゃうれしいんですよ。臆することなく英語でコミュニケーションをとってましたし、好きなこと、・熱中することがあるってええなぁ、と思いながら見守ってます。FreePractice2はシケインから観ようと決めていたので、1時間前から席確保。
ここ数年、毎年のようにご挨拶している親子さん。たまに別のイベントやレースでも会うことがあって、仲間感が育つのも楽しみなんです。ちょうどお会いしてる時に、読売新聞の取材が来て、お父さんが対応されてました。今年は海外メディアからの撮影やインタビューもすごかったし、何より中学生の彼のガスリー愛が届いて、毎年ピット前に入れてもらってたり、チームガスリーの一員として迎え入れられて、よそのお子さんやのにめっちゃうれしいんですよ。臆することなく英語でコミュニケーションをとってましたし、好きなこと、・熱中することがあるってええなぁ、と思いながら見守ってます。FreePractice2はシケインから観ようと決めていたので、1時間前から席確保。 途中の観覧車も去年から特別ラッピング。乗る時はドライバーを選べないので、タイミング勝負です。毎年長蛇の列。あ、チケットには金土日3日間の、遊園地乗り放題も付いてます。観覧車も対象なんですよー。手前のレーシングギャラリーも必見。歴代のF1マシンもエンジンも見られます。FP2はコースサイドの芝が、マシンからの火花で燃えるという赤旗が2回もあって、クラッシュでの2回と併せて、走行時間が短くなってしまって残念でした。シケインでしばらく余韻を味わってから、グランドスタンド裏のダージーパイを買って、「知り合いいないかなー?」って歩いてるとすぐ発見。しばらくおしゃべりして、GPスクエアのトークショーに行かれるときにバイバイして、自転車のある1コーナーゲートに向かいました。ピット出口のA席をのぞいたら、チームの人たちがランニングやサイクリングに行くところでした。
途中の観覧車も去年から特別ラッピング。乗る時はドライバーを選べないので、タイミング勝負です。毎年長蛇の列。あ、チケットには金土日3日間の、遊園地乗り放題も付いてます。観覧車も対象なんですよー。手前のレーシングギャラリーも必見。歴代のF1マシンもエンジンも見られます。FP2はコースサイドの芝が、マシンからの火花で燃えるという赤旗が2回もあって、クラッシュでの2回と併せて、走行時間が短くなってしまって残念でした。シケインでしばらく余韻を味わってから、グランドスタンド裏のダージーパイを買って、「知り合いいないかなー?」って歩いてるとすぐ発見。しばらくおしゃべりして、GPスクエアのトークショーに行かれるときにバイバイして、自転車のある1コーナーゲートに向かいました。ピット出口のA席をのぞいたら、チームの人たちがランニングやサイクリングに行くところでした。
レースのヒーローたちが解散前の大集合。見えにくいけど、オレンジのつなぎのオフィシャルさんたちです。この方々や、サーキットの担当者のみなさんが、芝火災の消火をして、予防のために夜中まで芝刈りして、水を撒いて、へとへとになって対策してくれたのに、土曜のFP3でまた燃えたっていう。春は乾燥してますからね。秋は台風にやきもきしますが、どっちがええんでしょうか!土曜日
FP3を見てから、イオンモールにイベント出店されているモータースポーツパークにお邪魔しました。
長男…写真ヘタクソやな…いろんなグッズとミニカー、チーム支給品のウェア、サイン入りの諸々、パンフレットや雑誌販売、レースシムコーナーや塗り絵、ペーパークラフトコーナーもフォトコンテストも写真家の作品販売コーナーもと、盛沢山すぎるワンダーランドです。Xでつながった方が、ここで店員さんをされると聞いたので、ご挨拶してきました。みなさんモータースポーツ愛がすごい。今回全然売り上げには貢献できなかったですが、いつフェルナンドが引退するかわからないので、1/12(デカい)が買えるように貯金しておこうと思いました。それから帰宅して予選を見て、日曜日も家からDAZNで決勝を観ました。土日に現地に行かなくて後悔するかな?と思ったんですが、意外と木金で十分F1気分は満喫できるんじゃない?ということがわかってしまった…?いやいや、現地の雰囲気はぜひ一度体感すべきです!一緒にサーキットグルメも楽しみましょう!あと、お得な駐車場情報もありますので、木曜から、年に一度の祭りに参加してみてください。と書いていたら、岩佐歩夢くんがなんと次戦バーレーンFP1でフェルスタッペンマシンに乗るとのニュースが!続々クビにし過ぎてリザーブが手薄になってしもうたのか(苦笑)純粋にあゆが評価されているのか?疑心暗鬼ですが見守ります!というわけで、私の発信があなたのヒントになりましたら幸いです。
では、またー。
ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』
This is my way. これは私のやり方です。
What is your way? あなたはどんな風にしますか?
The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。
ラジオ、聴いてくださいね!
過去放送分も配信しています。










